トラブルシュート¶
ここでは、SACMをお使いの際に問題が発生した場合の対処や切り分け方法を解説します。
コントロールパネルの操作¶
サービスアダプタの選択画面でチェックボックスを有効にできない¶
SAコードにDistribution IDが未割当の場合、オペレーションやコンフィグ反映時の選択画面において該当のSAコードは選択できません。
テンプレートセット、テンプレート変数の名前を入力できない¶
テンプレートセット名、テンプレート変数名は英数字(先頭は英字のみ)で入力する必要があります。
テンプレートセットのCSVファイルインポートに失敗する¶
CSVファイルのフォーマットの誤りや、パラメータの誤りが原因として考えられます。 以下の項目についてご確認ください。
変数名や変数値に対応していない文字が含まれていないか
各行、および各列の要素数は一致しているか
ヘッダ文字列([name]、[default])が所定の位置に記述されているか
変数名が空になっているものがないか
変数名が重複しているものがないか
変数の数が上限値を超えていないか
サービスアダプタの動作¶
サービスアダプタの接続が正常に完了しない¶
何らかの理由でサービスアダプタの接続が正常に完了せず、コンフィグ取得を繰り返す、もしくは起動処理が正常に完了しない、などの状況を指します。
まず、コントロールパネルからサービスアダプタのコンフィグ反映状態を確認します。アイコンの意味は以下の通りです。
状態アイコン |
アイコンの意味 |
|---|---|
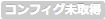
|
コンフィグ未取得 |
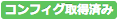
|
コンフィグ取得済 |

|
操作用接続確認中 |

|
操作・コンフィグ有効 |

|
コンフィグ操作中 |
さらに、詳細情報の「最終コンフィグ取得日時」および「最終操作可能通知日時」に表示されている日時を確認します。 これらの情報を組み合わせて確認することで、現在のサービスアダプタの状態を判断することができます。
状態アイコン |
日時表示 |
サービスアダプタの状況 |
|---|---|---|
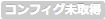
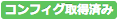
|
「コンフィグ取得日時」がサービスアダプタを起動した時より前の日時を示している |
|
「コンフィグ取得日時」はサービスアダプタを起動した時より後の日時を示しているが 、 「操作可能通知日時」がそれより前の日時を示している |
|
|

|
「コンフィグ取得日時」がサービスアダプタを起動した時より後の日時であり、 「操作可能通知有効日時」はさらに後の日時を示している |
|


|
- |
|
こちらの表のうち、実際に問題として想定されるケース a. と b. についてさらに詳しく解説します。
RS-Pull がそもそも成功していない
RS-Pull がそもそも成功しないケースでは、以下の問題が起きている可能性があります。状況に応じて機器の動作状況、回線の接続状況、サーバの設定状況を確認しながら対応を行ってください。
サービスアダプタから Internet への到達性が無い
サービスアダプタが接続されている環境にて、PPPoE や DHCP などのアクセス回線に問題があるケースです。通常の Internet 接続のトラブルシューティングと同様の対応を行ってください。なお、LS/RS に接続するため、上位のルータやファイアウォール機器にて HTTPS 通信 (443/tcp) が通過するよう設定されている必要があります。
サービスアダプタが SMFv2 モードにて動作していない
特定の機器 (SEIL シリーズなど) では、機器自体に SMFv2 モードで起動するか否かを切り替えるスイッチが存在します。そのような機器の場合、正常に SMFv2 モードで動作しているかどうか確認してください。具体的な確認方法については機器のマニュアルをご覧ください。
コンフィグ反映が行われていない
コントロールパネルでコンフィグが一度も反映されていないサービスアダプタは、コンフィグを取得できないため起動処理が正常に完了しません。コンフィグの編集を行った後に反映を忘れてしまうケースがありますのでご注意ください。
操作用接続確認に成功していない
操作用接続確認は、サービスアダプタが RS からコンフィグを取得した後、そのコンフィグで動作している状態で RS からの Push 操作が可能であるか実際に確認するフェーズです。
LS および RS からの Pull の際は、サービスアダプタおよび LS にあらかじめプリセットされたコンフィグを用いますが、操作用接続確認の際は、 それとは異なり RS から取得したサービスアダプタごとに異なるコンフィグを用いての確認となることに特に注意が必要です。
このケースでは、以下の問題が起きている可能性があります。
RS から取得したコンフィグで RS への通信が行えない
ほとんどがこのケースに該当すると考えられます。以下の事項を確認してください。
RS から取得したコンフィグで RS 自体に接続が可能かどうか
PPPoE のアカウント情報、経路設定、フィルタ設定などが適切かどうか
NAT 経由で接続されている場合、上位ルータの設定が適切かどうか
「接続待受型」固定で利用していて、サービスアダプタ側で待受が正常に行えていない
Push の際の操作用接続形式として、
接続待受型
接続持続型
のいずれかの方式を選択することができます。 「サーバ設定を使用」の場合、標準で待受型と持続型のいずれか利用可能な方式を自動的に選択することができますが、 接続待受型を固定的に選択した場合、サービスアダプタ自身が RS からの HTTPS 接続 (443/tcp) を受け付けられる状態になっている必要があります。 この場合、サービスアダプタ自身のフィルタ設定や、上位ルータのフィルタ、NAT 設定などを確認する必要があります。 なお、接続持続型を選択した場合はサービスアダプタから RS に対して HTTPS接続を行う形となりますので、特に制限はありません。
Heartbeat による監視が行えない¶
何らかの理由で Heartbeat による監視が行えない、接続断を検出できない、などの状況を指します。
Heartbeat による監視において問題となる以下の 2 つのケース
接続中であるにもかかわらず接続中と判定されない
切断中であるにもかかわらず切断中と判定されない
について解説します。
接続中であるにもかかわらず接続中と判定されない
このケースでは、Heartbeat パケットがサーバまで到達していないケースが考えられます。 Heartbeatパケットがサービスアダプタ自身や上位ルータ、ファイアウォール等でフィルタリングされていないかどうか、ご確認ください。 デモ環境ガイドに従って設定を行った場合、UDP の 10010 番ポートを利用しています。
切断中であるにもかかわらず切断中と判定されない
このケースは通常の運用状態で起こることは無いと考えられます。 なお、注意点としては、切断を検出するまでの時間がサーバ設定値によって異なるため、検出するまでに時間がかかることがあります。
Push オペレーションが行えない¶
何らかの理由でサービスアダプタに対する Push オペレーションが行えない状況を指します。
Push に失敗する要因は、サービスアダプタの接続状況によって異なります。 サービスアダプタの接続状況は、コントロールパネルの「現在の接続モード」の項目にて確認することができます。
それぞれの状況における原因を以下に説明します。
接続待受型で接続されている場合
接続待受型の場合、サーバ からサービスアダプタに対して HTTPS 接続が Push 操作ごとに発生します。 起動直後には Push 確認が行われている状態ですが、その後に接続状況が変化したり、 サービスアダプタ自身や上位ルータのフィルタ設定等が変更され、HTTPS 接続が行えなくなると Push に失敗します。
接続持続型で接続されている場合
起動中は常に HTTPS 接続が確立した状態となっているため、通常 Push 操作が失敗することはありません。